満足度指標の政策への活用について
2022年7月、経済社会システム担当では、「第5回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」(以下「コロナ意識調査」)、「満足度・生活の質に関する調査報告書2022」(以下、「満足度調査」)を公表しました。
コロナ意識調査は、感染症の影響下における人々の生活意識・行動の変化について把握することを、満足度調査は、経済社会の構造を人々の満足度(Well-being)の観点から多面的に把握し、政策運営に活かしていくことを目的とするものです。
今回は、これらの調査の意義や、背景にある人々の意識や行動の変化について、労働経済学がご専門である一橋大学の臼井恵美子教授にお話を伺いました。
コロナ禍を経た生活様式の変化について
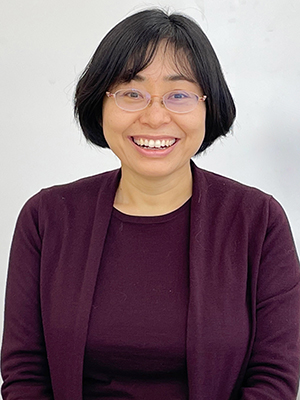
(臼井教授)内閣府のコロナ意識調査はコロナ下での生活様式の変化について分析するに当たって貴重なデータを提供しています。我々は第4回調査までのデータを用いて2022年10月に一橋大学経済研究所の松下美帆准教授らと共同で論文を執筆し、その後も第5回調査までの結果を用いて継続的に分析をしています。子育て世帯の家事・育児時間に着目すると、男性については、テレワークをしている方は増加しているのに対し、女性についてはテレワークをしている、していないにかかわらず増加していることがわかります。全体としては、男性は約5%ポイント、女性は約15%ポイントコロナ前と比べて家事・育児時間が増えており、女性の負担を減らすまでに男性の家事・育児時間が増えている訳ではないことがわかります。
(横山参事官)もともと女性と男性との間に家事・育児負担に大きな差があった中、コロナ下での児童・生徒の在宅学習等でさらに女性の負担が増えてしまったということでしょうか。
(臼井教授)そうですね。ただし男性の家事・育児時間が多少なりとも増えていることは確かです。
また、独身者の満足度に着目した分析では、生活満足度や健康満足度だけでなく、仕事満足度についてもコロナ後の回復が遅れていることがわかります。特に、社会とのつながりや生活の楽しさの満足度の指標が回復していないことを懸念しています。これらの指標についての今後の回復動向を把握するためにも、この調査は重要な役割を果たせると思います。
(石川調査官)我々はそこまでデータを深く分析することができていなかったので、研究者の方と意見交換することで大きな気付きを得ることができました。我々は速報性を求められる立場にあるため、臼井教授のような研究者の方による深い分析とうまく連携できるといいと思います。
生活意識や行動の変化に関するデータの重要性について
(臼井教授)コロナ下の生活意識や行動の変化に関し、政府以外が、このような半年ごとにタイムリー、速報性もある調査を行うことは難しい面があります。内閣府においてコロナを踏まえた人々の生活状況に関して詳細に調査をしていることは、政策立案の基礎資料を迅速に得るために極めて有効です。2020年度の国民生活基礎調査はコロナのために中止となっておりますが、そのような時期でも、今回の調査が実施されていた意義は大きいと思います。加えて、アンケート調査のデータをユーザーの求めに応じて提供する体制を構築していることは非常に有用です。
データの利活用に関しては、例えば、一橋大学の共同利用・共同研究拠点制度が実施しているプロジェクト研究に採択されれば、政府統計ミクロデータへの統計法33条申請が可能となるなど利便性の向上が図られてきました。しかし、時には、細かい地域単位ではデータを開示できないなどの制約もあります。地方自治体の独自施策については、過去の具体的な政策内容についての情報を得ることが難しいといったこともあります。データのオープン化については一層の改善が期待されます。
また、パネルデータの整備も重要です。コロナ意識調査では、コロナ禍前と比べての家族と過ごす時間や生活満足度について質問していますが、このような質問について、同じ回答者から継続的に答えていただくと、コロナ禍前の水準にいつ頃回復したかを知ることができます。
(横山参事官)現状では一部がパネルになっているだけなので、できるだけ継続的に回答してもらうようにすべきということですね。
(臼井教授)我々の分析では、コロナ禍の前からと比較した継続的な変化を見ています。既婚の方々に対する、夫婦の家事・育児の分担についての質問は第1~3回目までしか聞いておらず、コロナ発生から2年後の2022年以降における実際の家事・育児時間の変化は把握できたものの、男性が家事・育児分担が増えたと感じているのか、女性は負担が減っているかと感じているのかいずれも確認できていません。
(石川調査官)日本の男性の家事・育児参加の低さが問題となっていることからも、次回の調査では家事・育児分担に関する質問を充実させたいと考えています。
(臼井教授)これまでの調査を見ていると、テレワークをしている人たちが一定の割合に落ち着いている印象があります。第1回調査の際は働いている男性の38%、女性の19%がテレワークをしていたのですが、第2回目以降、それは男性25%、女性15%の水準となっています。過去にテレワークを経験した男性が、家事・育児時間を増やしたままである傾向もみえています。テレワークが、男性の家事・育児への参画を促進し定着させる面があるのではと思います。
テレワークについては生活満足度とも関係していますが、コロナ意識調査と満足度調査は今後どのように実施していくのでしょうか。
(石川調査官)コロナ意識調査はコロナ下でのテレワーク実施率を含む働き方の変化や家族と過ごす時間等の生活の変化、地方移住への関心や生活満足度等の意識の変化を中心に聞いています。他方、満足度調査ではWell-beingダッシュボードの作成に資するよう、継続的な質問を行うことを意識しています。今後、本日頂戴した御意見も踏まえ、両調査のバージョンアップに努めたいと考えています。
満足度調査の意義について
(臼井教授)政府の統計調査等において満足度を聞いている調査は少ない印象です。例えば、総務省が行っている社会生活基本調査は生活時間を詳細に聞いている貴重なデータがありますが、満足度や心の健康状態については直接的には質問されていません。そうした質問があれば、長時間労働が人々の仕事満足度や生活満足度にどのような影響を与えているのかを把握することができます。今回の内閣府の調査では、テレワークや働くこと、生活のことを聞きつつ、満足度についても聞いています。このような内閣府の取り組みが他省庁の統計調査にも波及すればと思っています。
(横山参事官)内閣府ではWell-beingに関する関係府省庁連絡会議の開催を通じて、関係府省庁のWell-being関連の基本計画等のKPI、取組・予算や調査・分析等の共有や優良事例の横展開を図っています。取りまとめ結果をみると、様々な分野において満足度やWell-beingに関する調査や事業が行われるようになってきています。また、従来は施策を実施すること自体が目標になりがちでしたが、人々の生活への影響や満足度にフォーカスがシフトしてきていることが感じられます。引き続き、関係府省庁の連携を図っていきたいと思います。
女性活躍の推進とデータを用いた分析について
(臼井教授)コロナ禍で特に忙しくなった医師の働き方については、女性活躍の観点からも分析の意義があります。診療科ごとの女性医師比率(45歳未満)を見てみると、産婦人科や麻酔科では女性比率が5割を超えている一方、外科、脳神経外科、泌尿器科、整形外科等の外科系診療科では女性医師の割合が1割程度です。近年、外科を選択する女性医師は増えてはいるものの、なぜ男性と女性で異なった診療科を選ぶ傾向があるのかを分析しました。具体的には、厚生労働省が実施している医師届出票を利用して、女性医師の初職診療科の選択の変化について分析しました。その結果、2004年に医師臨床研修制度が新たに改正されたことにより、女性研修医が外科を選ぶ割合が上昇したことがわかりました。改正前の臨床研修は単一診療科制だったのですが、改正後は複数の診療科を経験するスーパーローテート方式になり、外科のトレーニングを受けることから外科の面白さに気づくようになったということです。研修医制度の改正によって必修課程で実際に体験をすることから、個々の男女がジェンダーステレオタイプに影響されず、それぞれに真に合ったものを選ぶようになったいい例だと思います。
(横山参事官)女性が従来あまり進出してしなかった分野にチャレンジするという意識が広がってきている中で、新臨床研修制度がそれを後押ししたということであれば、他の分野でも同様の取組が効果を発揮するかもしれませんね。
(今井補佐)女性が新しい分野にチャレンジをしたり、高度な資格を取得することなどによる、女性の満足度の変化を測定した研究はあるのでしょうか。
(臼井教授)それはとても重要な視点です。医師のキャリア形成をみてみると、女性医師が男性の多い診療科を初職診療科として選び、そこに留まり、かつ、専門医資格を取得していることから、仕事による満足度が高まっているのではないかと思われますが、実際にそうなのか、今後研究していきたいと考えています。医師のキャリアに関してはジェンダー格差解消が進展している結果がみられています。一方、例えばアメリカでは、金融業界や法曹界においては、長時間労働を勝ち抜いた人が昇進し高い給与を得る傾向があり、このような「長時間労働プレミアム」のある産業には女性は参入しにくいとの分析結果もあります。また、女性の介護離職の問題は日本のみならず欧米でも深刻です。家族のための離職は、女性自身のキャリア形成に負の影響を与える可能性が高く、有効な対策についてデータを用いて一層の分析を行っていくことが重要です。
高齢化社会におけるWell-beingについて
(臼井教授)私が約7年前に書いた論文ですが、RIETI、東京大学、一橋大学が共同で実施した「くらしと健康の調査」という50~75歳を対象にしたアンケート調査を用いて、自営業者だった人か雇用者だった人かで引退後の生活が大きく違うということが分かりました。自営業者だった方は、定年制がなく、国民年金のみを受給ということで、ずっと仕事を続けています。そのため75歳になっても働き続けている人が多く、仕事を辞めるきっかけは体が悪くなったことが多くなっています。このような方々は、本当はもっと働く時間を短くしたいけれども、生活のためにそれができないという状態になっています。一方、若いとき雇用者だった方々は、定年退職を経験されており、厚生年金を受給していて、75歳で働いていない人がほとんど(約9割)でした。このような方々にアンケートを取ってみたところ、本当は働く時間をもっと長くしたいけれども、それができないという結果が得られました。このような方々の労働力、能力をもっと活用していく社会になるべきと思いますが、定年後に次の仕事を探すことは難しいという問題があります。ヨーロッパでは、定年を迎えるとフリーランスで働いたり、労働時間を大きく減らすなど柔軟な働き方に移行していく傾向がみられます。日本ではまだそのような働き方は普及していないと思いますので、その原因等を調べていくことが今後大事になっていくと感じています。
(石川調査官)日本でも新聞記者の方では60歳ぐらいに一度記者を辞めた後、契約記者となって、イベントのときのレポート等を作成したり、取材時に記者が足りない場合はサポートを行う、緊急事態が起きた際に手伝ったりなど、定年後に柔軟に働いている例もあります。週1~2日のみ働く、ある一定の時期にのみ働くといった、柔軟な働き方が確立されている業種もあるのかと思います。
(臼井教授)確かにそうですね。60歳~75歳までの男性の働き方を、日本とアメリカとで比較したところ、アメリカでは年に1~2か月ほどは休みながら働いていますが、日本では、年中ほとんど休まずに働いています。日本の場合は、働き方がインフレキシブルで、仕事はしたいが、もう少しゆったりとしたスケジュールで…と思っている方々に適したフレキシブルな働き方はあまり許されていないかと思います。
実際、アメリカ人の高齢者は働く時間に満足していると答える人が多いので、そこが日本の高齢者と異なるところです。前述のJSTARのアンケート結果で「あなたはいつまで働きたいですか」という質問に対し、「その他」の欄に「死ぬまで働く」という回答が結構ありました。米国ではこのような傾向はみられませんでした。また、「何のためにお金を貯めていますか」という質問に対して、「自分の葬式資金のために」という回答も若干ありました。これが日本的な考え方なのだと思います。
(横山参事官)リタイア後、何もしないのは孤独感につながりますし、高齢化社会において仕事を通じて生活の満足度を高めるにはどのような取組が必要なのか、国全体の問題としてしっかり考える必要があると思います。こういった観点からもWell-being関係の調査については鋭意やっていきたいと思いますし、そのような調査・分析において、行政機関と研究者がうまく補完しあえるような関係を築いていくことが重要であると考えています。
こどものWell-beingについて
(臼井教授)こどものWell-beingも重要なテーマです。「『少子高齢化における家族・出生・仕事』に関する全国調査」という調査に参画していますが、そこでは、働いているお母さんと働いていないお母さんとでお子さんの過ごす時間や発達度合いがどのように異なるのか、アンケート結果を基に解析を行っています。親との時間が減ることが子どもにどのような影響を与えるのか等、とても重要な問題だと思っています。
(今井補佐)親の満足度を測ることに焦点を当て過ぎず、子どもの心身、Well-beingがどのような状態にあるのか、子ども自身に聞くことも重要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
(臼井教授)子ども本人から回答を得るのはなかなか難しいので、親が子どものことをどう評価しているかという質問になる側面はありますね。子ども自身が、本当はどう考えているのか、それを知る調査を設計していくためには経済学者だけではなく心理学者、教育学者が協力して取り組んでいく必要があると思います。今後の課題としてそのような企画に参画することには関心はあります。
(今井補佐)家族で過ごす時間を増やすというのは、子どもが主体の話だと思います。子どもが成長していく段階で、Well-beingがどのように変化していったか、追跡調査等ができると興味深いと思いますがいかがでしょうか。
(臼井教授)厚生労働省が実施している21世紀出生児縦断調査があり、また、その他にも研究グループが単独で調査に取り組んでいます。子どもが成長していく過程についての情報があります。しかしながら、子どもたちを幼少からフォローアップし、さらには、就職し社会人になっていく状況を長期にわたって継続調査していくことは、資金面や人員やリソースを含む面で難しいです。そうした調査を推進するためには、一研究者だけで出来ることではなく、異分野の研究者、政策担当者が長期的な構想に基づいて、協力して取り組むことが必要であろうと思います。そのような流れになっていくことを期待しています。


