成長の新側面とGDPの進化、新たな手法の探求
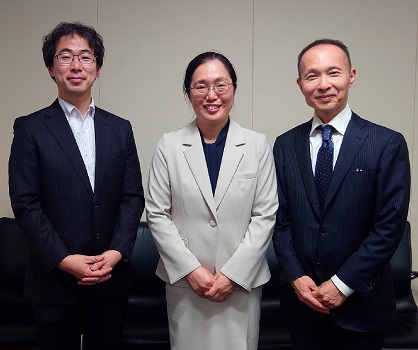
坂本 徳仁 東京理科大学教養教育研究院 教授、
外木 好美 立正大学経済学部 准教授、
村山 裕 内閣府経済社会総合研究所長
(本インタビューは、令和6年4月19日(金)に行いました。所属・役職はインタビュー当時のものです。)
坂本 徳仁
東京理科大学教養教育研究院 教授
外木 好美
立正大学経済学部 准教授
GDPは一国の経済活動を計測する代表的指標であり、経済学上の発明の一つともいわれます。また、経済構造の変化を踏まえて進化・発展を遂げています。一方、GDPにとどまらず経済・社会指標を構想する動き、いわゆる「Beyond GDP」の議論が国際機関などでみられ主観的指標などが注目されています。
今回、「Beyond GDP」の観点から、規範経済学などの理論が専門の東京理科大学教養教育研究院 坂本 徳仁 教授に、GDPの観点から、無形資産などの実証が専門の立正大学経済学部 外木 好美 准教授にお話を伺いました。
Beyond GDPへの関心の高まり
(村山所長)GDPは一国の経済活動を計測する代表的指標で、経済学上の発明の一つともいわれます。
一方、GDP以外の経済・社会指標にも関心が高まっています。いわゆるスティグリッツ委員会の活動もあり、Beyond GDPに関する議論が活発化しました。この背景について、理論経済学の学問的な成果も含め、お伺いしたいと思います。
(坂本教授)「Beyond GDP」という言葉が流行するきっかけになったスティグリッツ委員会は、2008年の金融危機を契機に、サルコジ仏大統領(当時)が、スティグリッツ、セン両教授に依頼し、政策目標となり得る包括的指標群の開発のために結成されたものです。その背景には、GDPだけにとらわれた結果として、金融危機を引き起こしたのではないかとの素朴な疑問がありました。
金融危機後、「ウォール街を占拠せよ」運動などが起きて格差への社会的関心が高まる中、地道に格差問題を扱ってきたアトキンソン、ピケティ、サエズらの研究成果も大きな関心を集めました。あくまでもGDPは総量、1人当たりGDPは平均値なので、格差も含めて、経済全体を見てほしいといった社会的要請に呼応した結果だと思います。
その上で理論経済学の成果についてお話しすると、伝統的な厚生経済学では、すでに1950~60年代から、総所得、GDP、集計的補償変分など何らかの集計量を使って社会の良さを論じること自体は、理論的に望ましくない、直接社会厚生関数を使って評価をしたほうがいい、と議論されていました。
ただ、当時の有力な経済学者、特にJ. R. ヒックスは、再分配が適切に行われてさえいれば、集計量と社会の良さを同一視してもよいと論じました(ヒックスの楽観主義と呼ばれます)。きちんと再分配を行うという前提の下、全体の取り分が増えることが大事とする立場で、結果としてその後も長らく集計量が重視されることになりました。
しかし、後の経済学では、再分配が怠慢を誘発しパレート効率性を損なうなど、再分配の負の側面を強調する議論が流行し、ヒックスの楽観主義から大きく乖離していくことになります。
こうした中、マーク・フローベイがBeyond GDPの報告書をまとめ、マシュー・アドラーなどの現代の規範経済学者らが再び社会厚生関数アプローチに戻ろうと唱えています。これが今の厚生経済学、理論経済学の見方になると思います。
(村山)経済が市場ベースに活動している以上、それを起点とした計測としてのGDPが活用されているのは確かです。また、GDP自体も経済活動の測定の観点から、経済構造の変化を踏まえてこれまでも進化・発展をしています。最近の経済構造の変化、専門家の関心の変化をどう見ていますか。
(外木准教授)私がGDPに関して、一番よりどころにしていたのはワイツマンの論文です。一定の想定の下でNNP(国民純生産)が社会厚生に近似される、という論文を大学院生のときに読み、GDPは教科書で学んではいましたが、感心しながら携わっていました。
当時、有価証券報告書、上場企業のデータベースを使って、設備投資や企業価値を扱うトービンのq理論を研究していました。財務諸表上に載っている数値は、どうしても有形資産に限られ、その限られている中で、企業をばら売りしたときの資本の価値と、実際に計測されている企業価値の比率であるqを試算してみたところ、奇妙な数字が出てくる産業がありました。教科書的にはトービンのqは1ですが、IT・情報関連産業の企業で、100とか、1,000といった数字が出てきました。それを見たときに、経済の重心が、測れない世界、有形から無形の世界に移行しているのだというところを体感しました。
計測していると、無形資産の割合はどんどん高まっていて、トービンのqを用いてどの資本によって生み出された価値かを分解できるのですが、近年、R&Dの企業価値創出への寄与が増加し、R&D以外のITも寄与している姿になっています。そういうものも含めて経済を計測しないと、どこから所得が発生していて、どう分配されているのかが分からず、経済のかじ取りが難しくなるだろうと思っています。
Beyond GDPの指標
(村山)国際機関などで、経済・社会指標を構想する取組があり、主観的指標も含めて注目されていますが、規範経済学などの観点から鳥瞰をお願いします。
(坂本)フローベイによる整理を援用すると、社会評価を行う政策目標となり得る指標としては、スティグリッツ委員会でも強調されたダッシュボード・アプローチ(複数の重要な指標群を作成し、包括的に判断する方法論)と、フローベイが「四銃士」と呼ぶ四つの指標を並列させながら、お互いの欠点を補い合う形で判断することがよいとされます。
「四銃士」の一つ目は、「社会指標」です。社会指標は、人々が人生で大事だと思っている諸分野(所得、教育、健康、安定性、自由、自然環境など)について統計を整理し、その平均や総量を見れるようにするものです。社会指標の例を挙げれば、人間開発指標やOECD Better Life Indexがあります。
二つ目は、1970年代から徐々に発展してきた幸福度、いわゆる主観的福利の指標です。研究では、従来思われてきた以上に経済的・物質的な条件と幸福の関係が緩やかで、社会的つながりが大事だと分かってきました。この指標は、経済政策の目標というよりも、国民全体のワークライフ・バランスや共同体の健全さを捉えるために利用できると思います。

三つ目は、等価所得指標で、この指標は社会厚生関数の中に直接取り入れられるべき個人の生活水準の指標になります。等価所得アプローチでは、何らかの不利な条件・属性(障がいや、教育年数の少なさ等)をもつ個人の生活水準を評価する際に、本人の評価に基づいて不利な条件・属性の分だけ個人の生涯所得を割り引きます。
四つ目は、潜在能力アプローチです。潜在能力とは「個人が人生においてどういう状態になり得て、実際に何ができるのかといった選択肢の幅」を指す概念で、等価所得と同様に個人の生活水準を示す指標になります。残念ながら、このアプローチの実用的かつ理論的に望ましい指標はまだ作られていませんので、今後、私たち理論家がこの指標をきちんと作らなければいけないと考えています。
(村山)今、挙げていただいた指標について、年々の評価がしにくい、指標を選択する上でのコンセンサスが得にくいなど課題があると思いますが、どう整理されていますか。
(坂本)例えば、社会指標だけを見ても100や200の指標が乱立するような状況であるため、公共政策上の意思決定が何もできないことになってしまいます。しかし、共通項が全くないわけではなく、乱立する指標間にさほどの違いはなく、本質的に大事だと思うことには合意が取れると思います。あとは国際比較が可能なように、各国政府で話し合い、学者とも連携して皆が絶対に外したくないと思う、多くても10程度の分野の指標をダッシュボードに載せ、それらの政策指標群を政策運営におけるKPIのような感じでそろえるのが順当だと思います。
(村山)理論的には魅力がありますが、GDPと同様の利用や整備は直ちには難しいとみられています。実装に向けての課題、また、今後の政策にいかす場合、どのようにしていったらいいのでしょうか。
(坂本)実務上の課題は、合意形成をし、各国で共通のデータを構築するため、専門部署や専門人材が必要だということ、これは非常に大変なことです。
理論上の課題としては、いくつかの論点で合意形成の途上です。例えば持続可能性の評価です。経済学には、マクロ経済学の王朝モデルのように未来の人たちの効用水準を一定の割引率で割引く手法がありますが、これを単純に用いると100年先、200年先の世代は実質的に無視する形で評価してしまいます。すると、100年先の人類への迷惑は考慮せず、今の私たちの消費水準を上げることが最良の選択となりえてしまいます。しかし、この結論はおそらく多くの人にとって到底受け容れられるものではありません。では、他の方法があるかというと、理論界でも議論が収束していません。
また、GDPはフローの尺度ですが、本当は経済成長率に一喜一憂するよりも、ストックも見るべきだと思います。日本のみならず、先進国はストックが十分にあり、これは現代的な生活を送れるということとほぼ同義です。途上国は成長率が高いですが、ストックとしてのインフラ整備は不十分です。フローはフローの尺度として見つつ、ストックも含め国の生活水準を見るという視点も必要だと思います。
GDPの進化:強み、及び可能性とは?
(村山)Beyond GDPの議論に対し、GDPへの注目や優位性は残っているとも思いますが、それはどういったところにあるとお考えでしょうか。
(外木)個人的に子育ての経験から、確かに経済成長しても自分の幸福感が上がらないというイースタリンのパラドックスは実感します。しかし、SNAは共通のルール・尺度で測るからこそ国際比較可能で、各国がGDPを整備するのは意義があると思います。
また、計測上の問題として、GDPは、市場評価というところがベースにあります。等価所得アプローチにおいて、各人の効用などをウエイトにして社会厚生を測るとされており、確かにそれができればすばらしいですが、人の幸せの本当の意味での価値、シャドープライスを測ることは、現実の統計整備では難しい現状があります。計測上の限界だけではなく、理論上の限界も提示した上で、共通のルールで測ってみたら、こうなったということを社会に提示することは大きな意義があると思います。
このように共通のルールで測り、数字として提示することは、専門家でなくても理解・評価しやすいものになるという利点があると思います。一番分かりやすいのは、景気動向指数で、生産、雇用、消費などの代表的な指標で簡易的につくるからこそ速報性があり、誰が見ても上がった、下がったと分かりやすいという価値があるのかと思います。
(村山)GDPの構成上、基礎統計を統合するという構造のため、変動の評価、把握が容易な面があると思います。続いて、経済構造の変化に応じたGDPの拡張、進化を具体的にどのように評価しますか。
(外木)有価証券報告書では、最近の経済の一番のエンジンである無形資産を計測できません。GDPが拡張され、そこを分析できるようになったのは非常に高く評価できると思います。
先ほどストックを評価すべきとのご指摘がありましたが、GDPの側も、フローで認識するか、ストックで認識するかで大きな違いがあると思います。理論上は将来の消費や生産を増やすことになる現在の支出が投資に当たり、無形であっても、将来の効果があるなら投資としてカウントすべきです。もしそれをフローとして認識し、ストックとして積み上がらないと認識してしまうと、ただの費用になり、コストカットの対象にさえなってしまいます。本来なら蓄積されて、将来、効果が出るものを、その分析ができないため、コストとして切ってしまうということが起こるのだと思います。
2008年の金融危機以降、経済成長は伸び悩んでいます。IT投資は1990年代後半から進みましたが、それは顧客の情報を把握したり分析したりしたいというニーズからなされてきました。すなわち、IT投資をするだけでは意味がなく、組織改革やマーケティング関係など様々な投資が進むはずでしたが、R&D投資や経済的競争力、組織資本などとIT投資との連動が低下してきています。
ストックとしてカウントし、経済効果が数字として見えれば意識するようになり、見えないとコストとして削ってしまうのではないかと思います。
(村山)無形資産の性格も踏まえ、経済・社会の発展の成果につなげていくにはどうすれば良いのか、他方で、社会厚生上どのような影響を与えることが考えられるでしょうか。
(外木)もともと資本減耗は、使って失ったものを、資本の全体量から減らすようにカウントされます。無形資産の場合はつくっても、経済的に成功するとは限らず、陳腐化が早いため、減耗が非常に早いです。減耗率の設定の仕方によってストックの積み上がり方も変わり、資本の限界生産性に等しくなるレンタルプライスも、利子率に減耗を加えて求めるため変わってしまいます。無形資産についても、積み上がったストックがどの程度継続して価値を持つかという調査があると有意義だと思います。
一方、無形資産の特性として、スケーラビリティー、サンク性、スピルオーバー、シナジーが4Sとして挙げられています。スケーラビリティー、つまり版権や権利さえ持っていれば、何個でもコピーでき、独り勝ちできる特徴があります。アイデアや新しい知識資産を使える側と、それに使われる側で格差が広がるのではないか、気になります。
実際に法人企業統計を用いた分析で、財務諸表で補足できるR&D投資のストック計測を行ったところ、投資をしてストックを持っている企業とそうでない企業に分かれてきていることが見えてきました。
Beyond GDPに関する議論と行政官の役割
(村山)ご議論いただいたとおりGDPは進化への取組を続けている一方、Beyond GDPが構想されています。こうした議論が与える私たちへの気づき、行政官に求められる知見、期待、また、学界と行政の分業・協業の在り方はどう御覧になっていますか。
(坂本)GDPは本当に必要な尺度であり、これだけ実務的に整っていて、国際比較・経時比較可能な指標は、ほかにありません。経済構造の変化や技術革新に従い進化を続け、総生産力の的確な指標として、今後も使われ続けるべきだと思います。
一方、それが社会の目的だと捉えるのは間違いで、あくまで国の経済全体の動きを見る尺度、経済政策の参考指標として使うのが望ましいと思います。
同時に、社会厚生関数だけを使うべきだとまでは言えないと思います。分配指標、自然資本指標、その他の物的ストックの指標、それらに関し、GDPと同じように国際的合意形成を図り、国際比較可能な尺度で社会評価できる指標群を整備していくというのが、行政官の方々に期待したいことです。
また、社会厚生関数で、一つの分配パラメーターを決めれば、それで全部社会評価できると考えるのは非現実的で、学界でも支持されていないと思います。パラメーターの設定は範囲で決めるべきで、極端な再分配を推奨するマキシミン型の社会厚生関数も、再分配を全く考慮しない功利主義社会厚生関数も、普通の人はいいと思わないはずです。合理的な範囲内の分配パラメーターを設定し、その範囲の幅の中で格差を評価するのが妥当なやり方でしょう。
なお、格差については、理論とは別に哲学の問題があります。哲学の問題を蚊帳の外に置いてしまう経済学者は多いですが、規範経済学では無関心というわけにはいきません。社会厚生上、総所得、皆で稼いだお金がどのぐらい大きくなるかという点と、格差、不利な立場にいる人たちにどのぐらい配慮するかということはしばしば対立します。哲学的に、なぜ格差が悪いのか、どういう格差なら問題ないかという判断基準が必要で、行政官含め私たち皆で哲学的な議論から学ぶ必要があると思います。
(外木)私は社会厚生ではなく、生産を測る立場ですが、経済構造が、サービス業中心に変わり、有形資産ではなくて、無形のアイデアや知識が最初のエンジンになってきています。無形資産への投資、すなわち無形資産を買う行為は、要はサービスの購入又は売上げですが、このサービス業でどれぐらい買ったかという統計がなく、ぜひ充実させてほしいと思います。次のSNAの改訂で、サービス業の供給・使用表をつくり、産業連関表をそこから作成するように変わると聞き、大いに賛同します。経済がサービス業中心に、無形資産に行くのだから、その分野の統計をしっかりつくってほしいと思います。その際、統計をつくる側も、それが何に使われ、どのタイミングで出せばGDP推計に役立つか気にするはずですから、省庁の協働を期待します。
また、学界の在り方としては、新しい計測方法はどんなものがあるかといった、最初のチャレンジのところは一緒にできるのではないかと思っています。

