経済・財政一体改革におけるEBPMの更なる進化に向けて
西内 啓
株式会社ソウジョウデータ 代表取締役
2015年に経済・財政一体改革推進委員会が設置されてから10年を迎えます。2020年からは本委員会の下にEBPMアドバイザリーボードを設置し、EBPM(証拠に基づく政策形成)の取組を強化してきました。2024年末には、政府の多年度にわたる重要政策及び計画を対象に、ロジックモデルや分析・検証方法、データの整備方針、政策への反映方法等を盛り込んだ「EBPMアクションプラン2024」を策定したところです。
今回は、本委員会で取り組むEBPMの更なる進化に向けて、EBPMアドバイザリーボードの委員を務めている統計家の西内 啓氏にお話を伺いました。
EBPMに対する意識の高まり
――近年、EBPMのようにデータを分析し意思決定することの重要性が認識されてきたようにも思いますが、この背景についてはどのように考えられますか。
(西内氏)最近の大きな変化と数十年にわたる変化があると思います。
まず、この数十年にわたる変化ですが、1992年にエビデンス・ベースド・メディスン(EBM、科学的根拠に基づく医療)という言葉が、公的な文献に初めて登場したそうです。
その少し前の1989年に注目を集めた論文があります。当時、経験的に不整脈にはこの薬を使う、という治療がされていました。ところが、実際にランダム化比較実験で効果を確認すると、理屈上は良さそうな治療で人が死亡していることがわかりました。データを使ってより良くしようというよりも、データを使わないと人が死亡してしまうことが医療の世界で認識されました。臨床疫学のようなニッチな領域がEBMと言い始めたところ、1990年代を通じてあっという間に、EBMが世界の常識となりました。
さらには、そのEBMがEBPMへ発展したのは、保健政策のような医療に近い領域は、エビデンス・ベースドにやらないといけないという認識がその時期に広がったためであると思います。開発経済などの領域も、医療や公衆衛生と関係が深く、そこから貧困対策のような経済的なものについてもEBPMの考え方が広がってきたと聞いています。
私がボストン留学中に耳にした例は、寄付で病院を建設することは一見良い行為ですが、その結果、地域医療が崩壊することがあるそうです。医療資源が非常に限られている貧困地域では、看護師や保健師は地域に一人しかおらず、その人が地域医療を支えています。そこに大病院ができると、待遇などからその人たちが引っ越してしまい、医療の空白地帯ができることがあるそうです。そのため、本当にQOL(生活の質)が上がるか検証してからでないと、大々的に進めるべきではないと開発経済でも言われるようになりました。
2002年にはブッシュ政権下で、教育系の法律である落ちこぼれゼロ法案(NCLB法)が成立しましたが、その中にエビデンスという言葉が100回以上登場します。良かれと思って実施した教育も意外と効果がない、効果がないわけではないがコストに見合っていないことは相当あります、という反省が徐々に世界に広まり、エビデンス・ベースドが当たり前になってきたというのが長期的なトレンドです。
そんな中、私が2013年に発売した本がヒットしました。ある方に聞いた話ですが、その前からEBPMのようなことに取り組みたかったが、上司に通じなかったそうです。ところが、上司が私の本を持っていたおかげで話がしやすくなった、という声もありました。
この1冊で43万部売れましたが、40万人もエビデンスに関わる仕事をしている人はいないと思います。しかし、43万部売れたということは、少なくともこうした取組を進めないといけないという発想が多くの人に行き渡りました。ですので、日本国内でのエビデンス・ベースドの大きな流れができたのは、やりたいけどできない、というようなハードルが下がったことがあるのではないでしょうか。
そして個人的には、そろそろ日本をどうにかしないといけないという危機感が広がってきたと認識しています。GDPがドイツに抜かれて4位です。中国に抜かれたときは、中国は人口が多いからと言っていましたが、日本よりも人口が少ないドイツに抜かれ、次はインドに抜かれるかもしれないという状況です。そろそろこのままだと良くないということで、世界情勢も非常に大変な中、これまで良いと思って作った政策は、本当に効果があるか、コストに対しリターンが十分か、といったことを考えないといけないとお尻に火がついたのではないかと考えます。

一体改革におけるEBPMの取組の成果
――EBPMアクションプランが昨年末にまとまりました。策定プロセスで感じられたことを教えてください。
(西内氏)霞が関の職員たちの本気を見ることができ、胸が熱くなりました。フィクションの世界で日本のエリートは検討ばかりで何も進まないという場面をよく見かけますが、現実はまったく異なり、それは嘘だと思いました。いざやるぞという時に、霞が関の職員たちが本気で知恵を絞り、責任を持ってやりきる姿を見ることができました。
――今回のEBPMアクションプランもそうですが、経済・財政一体改革におけるEBPMでは、個別の事業だけでなく、つながりなども含めて政策を広くみようとしています。この意義についてどのようにお考えですか。
(西内氏)非常に良いことです。企業では個別最適よりも全体最適を考えることが重要とされます。例えば、営業担当は営業のことだけを、マーケティング担当はマーケティングのことだけを考え、それぞれKPI(重要業績評価指標)が設定されているとします。そのKPIの達成のためだけであれば全体最適でない手段の方が良い、ということがあります。よくある例では、マーケティング担当は問い合わせや顧客リストの件数で評価されます。その際、絶対に注文する気がない人でも一万人集まりました、一人あたりコストはたった五円ですと言った方がマーケティング担当としては良いのです。しかし、いざゴールを考えると営業側はリストを渡されても、誰が買うのだということもあります。営業側は提案をした先のうち、どの程度受注できたかがKPIであったりするため、むしろ顧客のところに行かない方が、受注率が高くなるということもあります。
そうするとKPIの達成率は良いが、なぜ上手くいかないのかということになります。その企業が悪いということではなく、これはどこにでも起こりえます。やはり全員でゴールを共有し、管理すべき指標は不正しにくいものであることも大事です。加えて、事業の結果、影響を受ける側からのフィードバックをもらうことも大切だろうと思います。
――アクションプラン作成を通じて、実際の連携が高まるなどの効果を感じられましたか。
(西内氏)会社ですとビジョンとして我々はこういった会社を目指す、そのためにすべての仕事がある、というような、危機感が共有されます。アクションプランの作成を通じた空気の変化ということでいうと、我々は日本経済がこのまま衰退していくのではなく、再び世界のトップレベルで存在感を示す、ということが、明文化されていないとはいえ、皆さんで共有されたと思います。経済財政諮問会議においても、現状のままでは将来はこうなってしまうので、例えば少子化対策が一定程度上手くいき、生産性の向上に取り組むと、年間どれぐらいの経済成長が見込める、といった話が出てきたことは非常に象徴的だと思いました。省庁・分野横断的な視点で、日本を再び経済成長させるために、自分たちは何ができるかという知恵を絞ったことが、提出資料が良くなっていった背景にあると考えます。
――ビジョンの共有のほかに、ここ数年で担当者の意識の変化をお感じになったことはありますか。
(西内氏)先ほど申し上げたビジョンの共有は一番大きな変化と考えますが、それ以外では、EBPMがやらされるものから、本腰を入れて取り組んだ方が良いという意識に変わってきたと感じました。
最初は、この政策はRCT(ランダム化比較実験)などできないがEBPMは何をすれば良いか、ビッグデータを集めないといけないそうだが何を集めたら良いかよくわからない、という話が、地方だけでなく中央省庁の現場からも聞こえてきました。実際にはRCTができなくても良い、ビッグデータでなくても良いのですが、科学的根拠を作るということについて、情報を発信する人やそのリソースも増えてきて、具体的にプロセスを理解している人が増えてきたと考えます。その結果、全員ではないにしても、同期や上司・部下の繋がりで、EBPMについて理解している人の割合が高まってきたと思います。
EBPMの更なる進化に向けた課題
――政府のEBPMを一層進めるために、どのような視点が必要でしょうか。施策を見直して効果を高めるため、EBPMを広めていくためにどのような動機付けと工夫が必要と考えますか。

(西内氏)即効性がありそうなものを申し上げると、政策を検証する背景や方法、検証の結果からその政策がコストを考慮して良かったか悪かったかということを、統一したフォーマットで評価する仕組みがあると良いと思います。公開するか否かも含めて議論になると思いますが、少なくとも霞が関の内部では過去の事業の結果を調べることができるとともに、それには検証方法に問題がある、これでは失敗するが別の方法ではどうかなど、同じ仕事をする部署に知見が蓄積していきます。その一方で、ジョブローテーションで違う分野の担当者が異動してくると、その知見が継承されないことがあります。当然、海外の先行研究のレビューは必要ですが、一番参考になるのは、実際に日本国内の同じ事業でどのような手法が上手くいくのかどうかだと思いますので、過去に遡って追跡できるようにすべきです。加えて、その際にはあまり人事評価と紐づけない方が良いと個人的には考えます。研究者もこれまで良いと思われていた治療法が、実際には効果がありませんでした、と研究によって示すことは業績になっています。従来違いがあると言われていたことが実際には差がなかったというのは意外と重要な研究です。
10年ほど前は、研究者たちも出版バイアスがあると言われていました。出版バイアスとは、良かったもの、劇的な効果が出たようなものは公表されるが、そうでなかったもの、逆効果だったものは公表されにくいというものです。
そういった出版バイアスへの対処のために、医療の世界では臨床試験登録があります。このような検証をする、エビデンスをつくる、といった際に、一例目のデータが届く前に、必ずプロトコル(臨床試験実施計画書)を事前に登録し、変更があった場合は変更履歴がすべて可視化され、公開されています。
例えば、効果があったものばかりが公表されていても、100個のうち10個しか出ていないが残りの90個はどうかという検証をする際に、それには連絡先の記載もあるため、公開する必要はないが率直に効果がどうだったか、ということが追跡できる仕組みがあります。大手の主要なトップジャーナルは、臨床試験登録していないものは一切受け付けないことで、チェリーピッキング(都合の良い結果だけを選ぶこと)ができないようにしています。
これは政策も同様で、華々しい効果が出たのであれば素晴らしいですが、効果がなかったことも非常に重要です。例えると、落とし穴を見つけるのは大事なことです。これからここを通る人に落とし穴があるから来てはいけないと言えることは非常に良いことです。エビデンス・ベースドは説明責任を果たすためにも重要です。
先行研究や理論上において良いとされていることでも、実際に日本国内で検証した人がいないことを検証してみることは、価値があります。その時点で良し悪しがわからないからこそ検証をするのです。例えば医療の世界で良いだろうと思われていることをしない、逆に絶対に悪いであろうという実験をすることは倫理上良くありません。倫理的にわからないことは調べる価値があります。審査を通過しているのであれば、実際に実験をして間違いと見つけることは発見であり、むしろチャレンジは評価されます。その点、出てきた成果や結果だけで評価するようだと、みなさんがエビデンスには向かわないですし、落とし穴がわからないまま日本全体がさまよってしまいます。
――行政職員に向けて、データを扱う楽しさや面白さについて教えてください。
(西内氏)データに触れること自体も楽しいですが、個人的にはある種の懐疑主義やパンクスピリット(反骨精神)がないと、楽しさが半減すると考えます。儒教的な、年長者が言うことには従うことと、データに触れることは価値観としては正反対です。なぜエビデンス・ベースドに考える必要があるかといいますと、皆さんはそう言っているが本当か、絶対かという疑いがあるからこそ検証が必要です。アカデミックな発見は、従来言われていたことがそうではないと見つけることに意外性があって面白いのです。
もう一つは、ある種の裏技を見つけるようなところです。この問題は大きくなる気がした際に、データを見てみるとキードライバーが見つかったりするところがデータ分析の面白さです。ですので、真面目に勤勉に育てられてきた日本的な美徳とは逆サイドの方にいった方が面白いです。そういう人を許容できる組織の方が、データを使ってこれをすれば良いという裏技が見つかります。従来は間違っていて今ひっくり返した方が絶対に世の中のためになる、といったことがあった方がデータを触っていても面白くなると思います。
また、権威に対して自分が若くて何も発言権がない、ということを覆す手段でもあります。これは本当か、何か違うかもしれない、ということに対して、経験がなくてもデータの中には経験しきれないほどの情報量があります。例えば、一万人のデータは一万人の人生経験を凝縮していますので、これをうまく使うと、その一万人に聞いたらこう答えるであろう、というところが出てきます。そうすると、長年の業界や仕事での経験が、世の中の変化によって価値観が変わっていることもあれば、逆に大昔の経験が今こそ非常に大事ということをデータから掘り出せることもあります。若さから発言を重く受け止めてもらえない人ほど、データを扱うと良いと思います。
――多くの行政職員は数年単位のジョブローテーションで業務が変わります。そうした状況下で、民間との連携を含めて、どのように人材・ノウハウ不足を改善していけば良いかについて、お考えをお聞かせください。
(西内氏)昔と今で異なる点として、定量的な分析を行う研究者は文系の学問でも増えてきていると思います。お勧めは、新しい仕事に着任した際に、その分野で定量的な研究をしている人は誰であるか、ということを最初に知っておくことです。例えば、教育では従来の定性的な話や制度的な話についてデータを取って研究している方はいますし、経済系でも増えてきています。数理モデルという話でなく、実証研究が増えてきています。その領域でどの研究者が重要かということについては、例えば、科研費を誰に出しているか、JST(科学技術振興機構)のプラットフォームで総説論文を誰が書いているかなどを調べることができると思います。
それをエビデンスとして活用する際に、手軽な方法の一つは、有識者会議にその人を呼ぶことです。ただし、エビデンスのピラミッドと呼ばれるものでは、有識者の意見は一番エビデンスのレベルが低く、それよりも事例が上ですし、その上は数百件でもいいのでデータ分析をした結果、となります。有識者に対して、専門領域での先行研究の調査事業をお願いする、などのオプションが増えると良いと思います。
今、大学の事業を手伝っていますが、大学は多くの場合、外部資金を獲得しても使い道や使いきるべき期間に大きな制約があり、企業経営的な視点で見ると難しさを感じています。急にアルバイトのように研究者を雇うことは困難であるため、その仕組みはどうだろうかと個人的には思います。私が11月に新会社を立ち上げ、研究機関から委託を受けようとした際、調達資格が必要ということで、書類をそろえて提出しました。資本金の小さい若い会社は受託できる事業の金額がかなり強く制約されているようでした。
忙しい行政職員が皆で文献レビューや先行研究の調査などに取り組むことは現実的ではないと思います。レビューをまとめて報告書を作る際に戦力になるかどうかには、その分野でトレーニングを受けた経験のほかに知的体力のようなものも重要で、大手企業などより若者たちが作ったスタートアップの方が、パフォーマンスが高いことも考えられます。しかし、公共調達にあたって彼らが大手企業よりかなり不利というのは一考の余地があるかもしれません。
――中小の事業者であっても、しっかりと信頼のおける機関と連携できる仕組み作りが必要と。
(西内氏)役務提供ですので、最終的に納品物が出ないなら費用が支払われません。エビデンス・ベースドというお手伝いの部分で言えば、会社の資本金などの財務面は気にしなくても良いのではと思います。
いずれにせよ、大学やアカデミックな背景があるシンクタンクなど、調査業務ができる先とご縁を持つと良いと思います。若手の行政職員からすると、大学時代のゼミの同期や先輩・後輩も多くいるため、いざというときに分析をお願いしやすいのではないでしょうか。
医療の世界でも分析ができる医者ばかりではないです。とはいえ、文献が出てきた際や、製薬会社がデータを提出した際に、それをもとにいきなり実践するのではなく、それが本当かどうかを確認するという批判的な吟味が必要です。
医療の世界のSTROBE(ストローブ)というガイドラインは観察研究の報告のためのものですが、書きぶりのチェックリストでもあり、批判的に読もうとする際には、どのように報告されているかについてガイドラインとともに読むことが非常に大切です。自分では分析できないが、他人の分析結果を読み解いて批評できると、やり直しができるかもしれないですし、自分の知りたいことに対する答えが別の場所にないかという探索もできます。ジェネラリストになればなるほど、批評のリテラシーは重要になるように思います。
――今回のEBPMアクションプランをまとめる中で、新しいデータの整備が必要との指摘がありました。今後、ビッグデータや新しいデータを活用していく上で注意すべき点などについて、教えてください。
(西内氏)先ほど申し上げた臨床の世界にはデータマネージャーという専門職があります。医療機関ではカルテや検査結果を電子化し、データが蓄積されています。それらをいざ研究で使う際には、医者が直接ITにアクセスするかというとそうではないのです。臨床研究でこういう設計で調査をしたいというときに、データをきれいな状態で保ち、データの中身を確認したいときにすぐ答えてくれるクリティカルマネージャーのような専門職があります。
企業でも行政でも特にデータマネジメントが不足していると思います。公的統計などの従来の使い道に関してはデータマネジメントができています。しかし、調査票情報の二次的利用や省庁を跨いだデータ活用の必要性は増加していますが、対応が十分とは言えません。自分たちが持つデータを誰かが全て把握し、整合性の確認に本腰を入れて取り組む必要があります。例えば、歴史的な背景で、事業所の従業員数のカテゴリーが統計の種類によって異なるなどの問題があります。特定の部局にデータが一元化されていると、知りたいことはそこに聞けば良いというようになります。そのような専門組織がないにしても、データマネジメントは良くなっていると感じます。例えば、経済センサスは異なる時期に異なる調査をしていて、データ同士の関連性が不明瞭でした。それがそろってきたということは、みなさんの意識が経済や企業に対してはそろえた方が良いとなったということでしょう。大変だったのではと思います。
そこがしっかりしていると評価の際にどこを見れば良いか、要するにKPIをどうモニタリングするかが分かります。不足があれば独自で調べる必要があり、その調査にもコストがかかるが、事業期間が5年間のなかで2年目だけに公的統計調査のタイミングがあるならば、ずらした方が良いといったこともあります。
さらに、科研費を取って独自調査をしている人は同じようなことを複数の人が独自でやっているせいで、医療機関には調査疲れがあります。調査に回答したが同様の調査がまた来たといったようなものです。例えば、基本属性はこの公的統計を見てください、回答している施設や公的機関に関して、このデータをベースにしつつ追加でアドオンする定期的な調査をするので、ここで聞きたいことがあれば案を出してください、ということができると思います。専門組織が重複を調整するというような形にすれば、無駄な調査を減らせるのではないでしょうか。
――EBPMに合わせてそうしたデータ収集の効率化を一緒に進められると良い取組になりそうですね。
(西内氏)ビジョンが省庁横断的に統一されていれば、常にモニタリングする必要があるものが、基幹統計として整備しやすくなると思います。
――国だけでなく、地方自治体が保有するデータをさらに活用していくにはどのような対応が必要でしょうか。
(西内氏)まず一つは、フォーマットをそろえることが非常に大事です。ITではサービスレイヤーという言い方をしますが、窓口のサービスは着々と標準化が進んでいます。どの程度、裏側のデータが統一されるかも大切だと思います。主要なところはさすがにそろえるにしても、そうでないところも標準化されると、おそらく比較が可能になると思います。ただし、そもそも学校や教育委員会がデータを持っているかどうか、といった懸念はあります。
加えて、様々な施策を各自治体が進めていますが、同じタイプの施策をどこで実施して、どこで実施していない、というデータをお互いにそろえた方が良いと思います。そうすれば、ある時期にこういった施策をこの地域は先行して実施していた一方、この地域は実施していなかった結果、同じような規模感や環境のすぐ隣の町でどれぐらい差がついたといったことが、分かるようになります。それもある種のデータマネジメントです。
進め易さでは国のフォーマットをそろえるほうがまだ楽で、地域を全部そろえるほうが大変です。しかし、国側がちゃんと統一される中で、地域側も標準フォーマットが出てくると、やりやすくなっていくと思います。
一体改革を通じて目指す経済・社会の姿
――経済・財政一体改革のEBPMを通じて、どのような経済や社会が実現していくことを期待されていますか。
(西内氏)会議の場でも申し上げましたが、経済成長を諦めないことが重要です。以前、日本の人口は減少するが、心の豊かさが大切だと言った人がいました。それは経済的に豊かであるからこそ、財産を食いつぶしながら幸せな生き方ができるということだったのかもしれませんが、今ではその余裕はありません。
少子化対策も必要ですが、少子化で人口が減少するから経済成長できないというのは、エビデンス上は正しくありません。人口が増加しても経済成長していない国は世界にいくらでもあります。
経済学で人口より大切と言われているのはイノベーションです。人口当たりの論文数や特許の件数、教育の水準、研究開発投資のGDPに占める割合などが重要で、これらは経済成長を牽引していくと言われています。にもかかわらず、日本経済は衰退すると悲観的に他人事のようにいいますが、そうした思い込みこそが経済を衰退させていると思います。イノベーションや研究開発、教育に本気で取り組めば、経済は成長すると思います。
それこそ明治維新後の日本の急速な経済成長は、世界史的に非常に珍しい事象です。歴史的な研究で、当時の国の事業予算のうちのどれぐらいを研究開発に使っていたかというと、7割ぐらいつぎ込んでいました。欧米以外で先進国になる国が出てくるとは予想されていなかった中で、日本はちゃんとキャッチアップしたのです。戦後の日本の復興も東洋の奇跡と呼ばれましたが、明治維新からの経済成長もそれに勝るとも劣らない奇跡でしょう。それが限られた予算を全力で海外の技術者の招へいや、あるいはそれを翻訳するための予算に使ったという歴史から私たちは学ぶべきです。それぐらいの本腰を今入れられるかというと、社会保障の問題があり難しいかもしれません。
ただ、社会保障は非常に大事ですが、研究開発投資に加え、教育や少子化対策も次世代のためになります。本当にちゃんと検証すると、ものによっては借金をしても将来的に黒字になるから実行すべき、というものが一定数はあると思います。それがどこであるかを正確に見極め、次世代のための投資をしていくことができれば、経済は成長するはずです。
あまり考えずに投資だと思って実は浪費していたり、投資ではないところばかりにお金を使ったりしていると、経済は成長しないと思います。国内のパイを増やした上で再分配を進めることができれば、貧困、犯罪といった解決できる課題はまだまだ日本でいくらでも残っています。経済成長を続け、日本のような自由で民主的な国が存在感を示すことが、世界の他の国にとっても良いことだと思いますので、改革に本腰をいれていけると良いと思います。
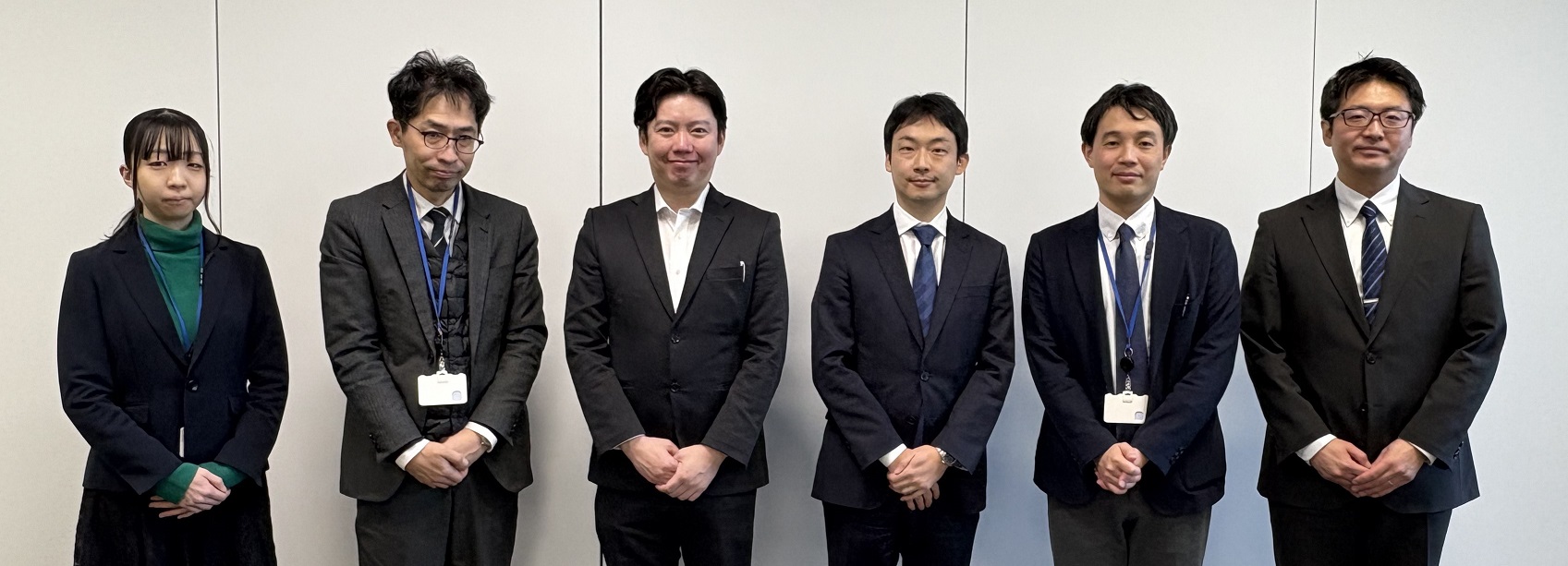
左から
内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付 小澤 花、
同付参事官 小堀 厚司、
「EBPMアドバイザリーボード」西内 啓委員、
内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付 上席政策調査員 井上 肇、
同付参事官補佐 千葉 隼人、
同付 石田 将康
(本インタビューは、令和7年1月17日(金)に行いました。所属・役職はインタビュー当時のものです。)

